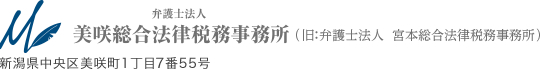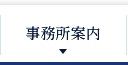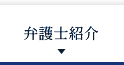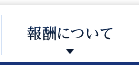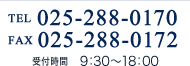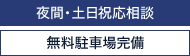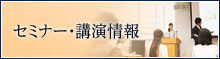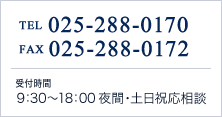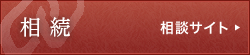刑事事件で弁護士ができること
弁護士は刑事事件の段階によって次のようなことを行ないます。

|
捜査段階 (逮捕・勾留期間) |
・被疑者との面会、取調べに対する対応を 助言 ・被害者との迅速な示談 ・勾留に対する異議の申立て(準抗告) ・仕事上の緊急な連絡等 |
|
公判請求~判決 |
・公判に向けての証拠収集 ・被告人の保釈請求 ・公判での活動(証人尋問、弁論)等 |
■捜査段階
捜査段階においては、被疑者と何度も面会を行い、事件の背景を含めた全体像を理解し、弁護活動を行います。
被害者のある犯罪の場合、被疑者に対する検察官の処分(不起訴、罰金、公判請求等)にとって、一番影響を与えるのが、被害者との示談が成立しているかという点です。そこで、弁護士としては、第一に被害者との示談を行うべく活動します。
また、事案によっては、勾留が違法と考えられる場合があります。勾留は、被疑者に逃亡の恐れがある、罪証隠滅の疑いがある、住居不定であるといった場合に行われますが、これらのいずれにも該当しないにも関わらず、勾留がされてしまうことがあります。こういった場合には、身柄の早期解放に向けて、勾留に対し異議を申し立てます(勾留に対する準抗告)。
 被疑者は、予告なく、突然に逮捕されます。そうすると、仕事をしている場合など、緊急に対応しなければならないことが出てきます。こういった場合、弁護士が代わりに会社に電話をする、また家族に一定の対応をしてもらうこともあります。
被疑者は、予告なく、突然に逮捕されます。そうすると、仕事をしている場合など、緊急に対応しなければならないことが出てきます。こういった場合、弁護士が代わりに会社に電話をする、また家族に一定の対応をしてもらうこともあります。逮捕された被疑者は、外界の情報が全く入らなくなることから、大変な不安を感じます。こういった被疑者に情報を与え、安心させてあげることも、弁護士として重要な活動だと思います。
■公判請求~判決まで
勾留期間が終わったところで、検察は、被疑者に対し、一定の処分を行います。
一つは、不起訴ということで、処分はなく釈放されます。また、罰金の場合には、罰金を支払う必要はありますが、ひとまずは身柄は解放されます。
しかし、公判請求(裁判をするということです)をされた場合には、判決がなされるまで身柄拘束が続きます。判決がなされるまでの期間は、もちろん事案によって異なりますが、数か月程度が多いと思われます。
公判請求がされた場合、弁護士としては、保釈の可能性を検討し、身柄の解放のために活動をします。また、裁判に備えるため、証拠収集活動を行います。これは、犯罪を行っていないとして争っている場合はもちろん、そうでない場合にも必要な活動です。
 すなわち、罪を犯した人にも相応の理由があり、また犯罪とは直接関係がなくとも、その方には見るべきところがあるかもしれません。しかし、弁護士が活動をしなければ、こういった事情は裁判には出てこない結果、事件全体をとらえた適切な判決はなされません。裁判は、被告人にとって、一方的に不利なものとなってしまいます。
すなわち、罪を犯した人にも相応の理由があり、また犯罪とは直接関係がなくとも、その方には見るべきところがあるかもしれません。しかし、弁護士が活動をしなければ、こういった事情は裁判には出てこない結果、事件全体をとらえた適切な判決はなされません。裁判は、被告人にとって、一方的に不利なものとなってしまいます。こういったことからしても、たとえ犯罪を犯したことを認めている事件であっても、弁護士による活動は不可欠です。
刑事記事一覧
1.ご家族・ご友人が逮捕されてしまった方へ
2.弁護士に依頼するメリット
3.刑事事件で弁護士ができること
4.国選弁護人と私選弁護人の違い